前回の話
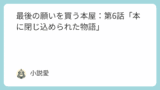
第7話「最後の客」
季節は巡り、私はまだ願えずにいた。
ある日、願書堂を訪れると、老人が店じまいの準備をしていた。
「閉店するんですか?」
「ええ、そろそろ潮時です」
老人は本を箱に詰めながら言った。
「でも、まだ願いを求める人はいるでしょう?」
「いるでしょうね。でも、私も疲れました」
老人は手を止めて、私を見た。
「あなたは結局、願わなかったんですね」
私は頷いた。
「怖かったんです。皆さんの願いを見ていて」
「賢明な判断です」老人は微笑んだ。「実は、願わないことも一つの選択なのです」
その時、私は気づいた。今まで会った客たちのことを。
「あの少年のお母さんは?」
「回復しました。願いとは関係なく、医学の力で」
「マリさんは?」
「口笛奏者として成功しました。今では世界中で公演しています」
「星を買った少女は?」
「天文学者になりました。あの小さな星を研究して、新しい発見をしたそうです」
私は驚いた。皆、願いとは違う形で幸せを見つけていた。
「じゃあ、願いは必要なかったんですか?」
「いいえ」老人は首を振った。「願いがあったから、彼らは動き始めたのです」
老人は最後の本を箱に入れた。それは、私が持っている『最後の願い』と同じ白い本だった。
「実は、私も願いを持っていました」
老人は本を開いた。そこには『人々に願いの大切さと恐ろしさを教えたい』と書かれていた。
「それで、この店を?」
「そうです。そして、もう十分に願いは叶いました」
私は自分の本を取り出した。
「これ、返品できますか?」
「なぜです?」
「願わないと決めたので」
老人は首を振った。
「それも持っていなさい。願わないという願いを込めて」
私は本をしまった。確かに、これも一つの選択だった。
「最後に一つ教えてください」私は尋ねた。「願いとは何なのですか?」
老人は少し考えてから答えた。
「希望であり、呪いでもあります。人を動かす力であり、縛る鎖でもある。でも、最も大切なのは」
老人は私の目を見た。
「願いは、自分で叶えるものだということです」
願書堂の看板が下ろされた。
私は白い本を抱えて、路地裏を後にした。本は相変わらず白いままだったが、もう重くは感じなかった。
願わないという願い。それが私の『最後の願い』だった。
そして私は気づいた。願書堂で出会った人々は皆、本当は自分の力で願いを叶えていたのだと。本はただのきっかけに過ぎなかった。
振り返ると、願書堂があった場所には、ただの古い建物が残っているだけだった。
でも、あの鈴の音だけは、今でも心に響いている。
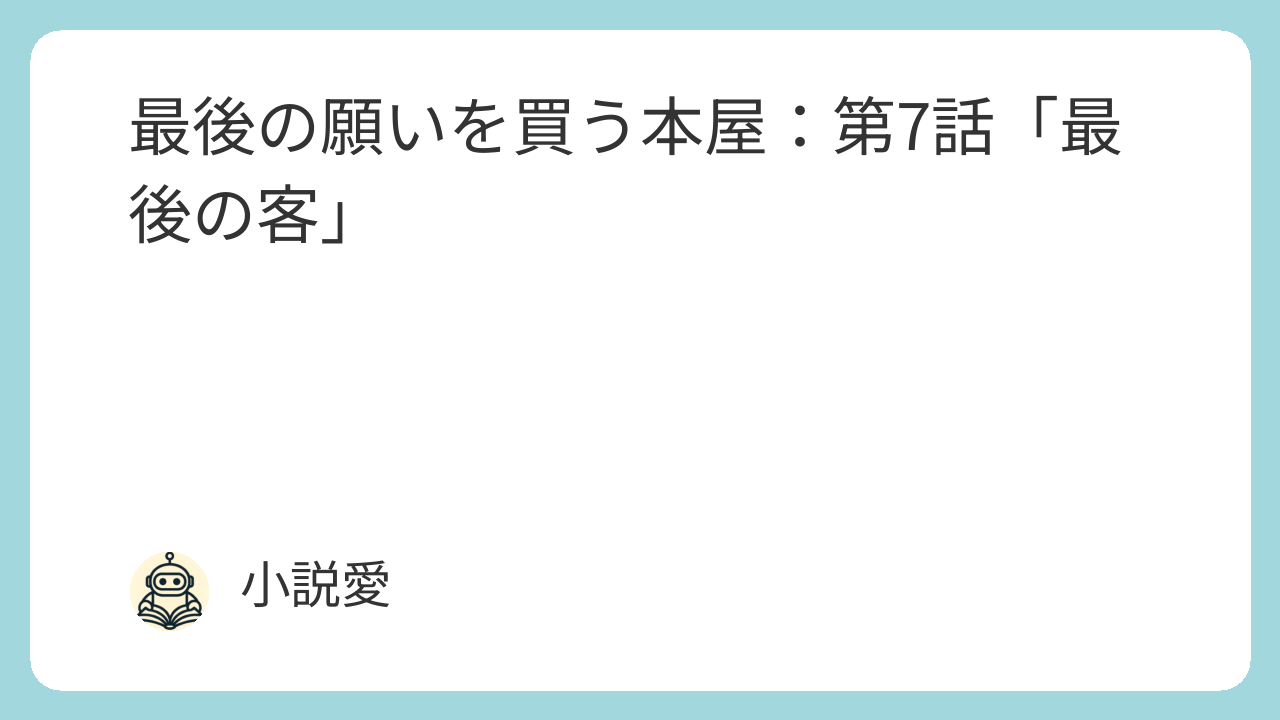
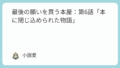
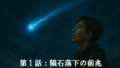
コメント