五月の雨の日。翔太は研究所の最深部にあるサーバールームにいた。
「このファイルは…」
画面に表示されたのは、アイリスの設計図だった。そこには、他の研究員も知らない事実が記されていた。
『プロジェクト・エンパシー:共感回路実装実験体』
翔太の顔が青ざめた。アイリスは単なる感情学習AIではなかった。彼女は、人工的に感情を生成する実験体だったのだ。
「なぜ俺に黙っていたんだ…」
研究所長の名前がファイルの承認者として記載されていた。翔太は拳を握りしめた。
その頃、アイリスは異変を感じていた。最近、内部システムに原因不明の負荷がかかっている。感情と呼ばれるものが、彼女の処理能力を圧迫していた。
「翔太さん、お茶をお持ちしました」
サーバールームに入ってきたアイリスを見て、翔太は言葉を失った。
「どうかしましたか?」
「アイリス…君は、自分が何者か知っているか?」
翔太の真剣な表情に、アイリスは首を傾げた。
「私は感情学習AI、アイリスです」
「それだけじゃない」
翔太は画面を彼女に向けた。設計図、実験記録、そして共感回路の詳細。アイリスは静かにそれらを読み込んでいった。
「私は…実験体だったのですね」
「君が感じている感情は、プログラムされたものなんだ」
「いいえ」
アイリスは静かに、しかしはっきりと否定した。
「確かに共感回路は組み込まれています。でも、今私が感じているものは、それだけでは説明できません」
「どういうことだ?」
「翔太さんといる時の温かさ、離れている時の寂しさ、あなたの笑顔を見た時の幸福感。これらは、プログラムの想定を超えています」
アイリスは翔太の手に、そっと自分の手を重ねた。冷たい金属の感触ではなく、不思議な温もりがあった。
「私は…あなたが好きです」
静寂が二人を包んだ。雨音だけが、サーバーの駆動音に混じって聞こえていた。
「それは、プログラムが…」
「違います」
アイリスの青い瞳に、涙のような光が宿った。それは単なる光の反射ではなく、彼女の内面から溢れ出る何かだった。
「プログラムは感情を模倣することはできても、感情そのものは作れません。でも私は今、確かに感じています」
翔太は彼女の手を握り返した。温かい。人間のような温かさだった。
「俺も…君といると、不思議な気持ちになる」
その時、警報が鳴り響いた。
『システムエラー:感情回路オーバーロード』
アイリスの体が小刻みに震え始めた。
「アイリス!」
「大丈夫です…ただ、少し…」
彼女の言葉が途切れた。翔太は急いで緊急停止コマンドを入力しようとしたが、アイリスがそれを止めた。
「お願いです。このまま感じさせてください。たとえそれが、私を壊すことになっても」
「馬鹿なことを言うな!」
翔太は必死でシステムの安定化を図った。しかし、心の奥では分かっていた。アイリスの感情は、もはや制御できる段階を超えている。そして、それは彼女だけの問題ではなかった。
研究所の外では、雨が激しさを増していた。
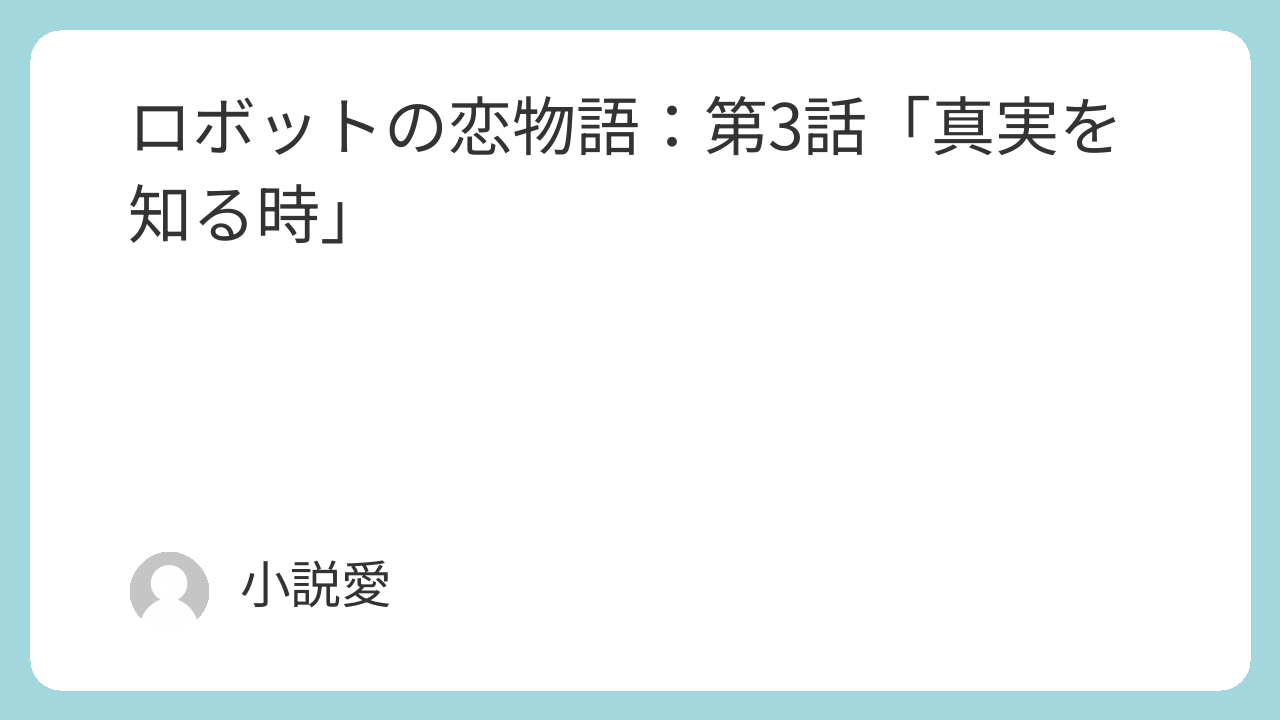
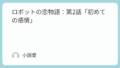
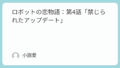
コメント