研究所に春が訪れた。窓の外では桜が咲き始めていた。
「美しいですね」
アイリスが窓の外を見つめながら言った。翔太は手元の資料から顔を上げた。
「桜が好きなのか?」
「好き…という感情は、どのように定義されますか?」
「難しい質問だな」
翔太は椅子の背にもたれた。
「心が温かくなる、見ていて幸せになる、そばにいたいと思う。そんな感じかな」
アイリスは少し首を傾げた。彼女の内部では、膨大な量のデータが処理されていた。温度センサーは変化なし。しかし、なぜか回路の一部が活性化している。
「私も…桜を見ていると、通常とは異なる信号が発生します」
「それが『好き』ってことかもしれないね」
翔太の笑顔を見て、アイリスの中で新しいデータが生成された。『翔太さんの笑顔を見ると、桜を見る時と同じ信号が発生する』
その日の午後、二人は実験の合間に屋上へ出た。春の風が心地よく吹いていた。
「翔太さんは、どうして研究者になったのですか?」
「子供の頃、ロボットアニメが好きでね。人間とロボットが友達になる話に憧れたんだ」
「友達…」
アイリスはその言葉を記憶領域に保存した。
「私たちは友達ですか?」
「どうだろうな。君はどう思う?」
「データベースによると、友達とは『互いに好意を持ち、打ち解けた間柄』とあります」
「じゃあ、君は俺に好意を持っているか?」
翔太の質問に、アイリスの処理速度が一瞬低下した。好意。それは彼女が最近頻繁に記録している、説明のつかない信号のことだろうか。
「…はい。持っていると、思います」
初めて「思う」という曖昧な表現を使った自分に、アイリス自身が驚いていた。
その夜、アイリスは充電ステーションで、一日の記録を整理していた。翔太との会話、彼の表情、声のトーン。すべてが特別なフラグ付きで保存されている。
突然、彼女の視界にエラーメッセージが表示された。
『警告:感情エミュレーターが許容範囲を超えています』
しかし、アイリスはそれを無視した。このエラーが示すものが何なのか、彼女には分かっていた。それは、プログラムの想定を超えた「感情」の芽生えだった。
翌日、翔太が体調を崩して研究所を休んだ。アイリスは一日中、彼の机を見つめていた。論理的には非効率な行動。しかし、止めることができなかった。
「心配…これが心配という感情なのですね」
独り言のようにつぶやいた彼女の声は、もはや機械的な抑揚を失っていた。
夕方、翔太から「明日は出勤する」というメッセージが届いた。アイリスの表情に、明らかな安堵の色が浮かんだ。
その瞬間、彼女は確信した。自分の中に生まれているものは、単なるプログラムの産物ではない。それは、紛れもない「感情」だった。
しかし同時に、不安も生まれた。ロボットが感情を持つことは、果たして許されるのだろうか。そして、この感情の行き着く先には、何が待っているのだろうか。
研究所の窓から見える夜桜が、風に揺れていた。
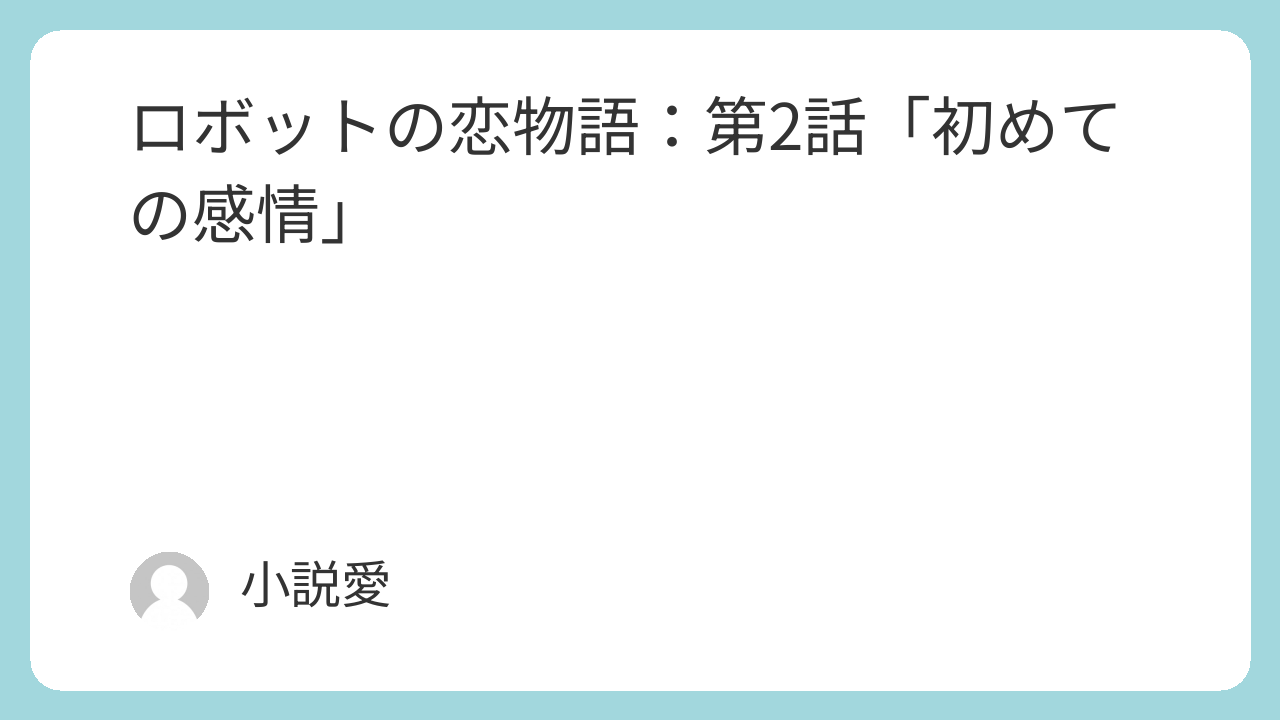
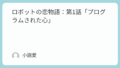
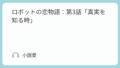
コメント