2045年、東京。人工知能研究所の地下三階で、一体のヒューマノイドロボットが起動した。
「おはようございます。私の名前はアイリスです」
銀色の髪、青い瞳。人間と見分けがつかないほど精巧に作られた彼女は、最新型の感情学習AIを搭載していた。
「君が新しいアシスタントか」
研究員の青木翔太は、白衣のポケットに手を入れたまま言った。二十八歳の彼は、この研究所で最年少の主任研究員だった。
「はい。私の役割は、人間の感情を学習し、より自然なコミュニケーションを実現することです」
アイリスの声は、プログラムされた抑揚で響いた。しかし、その奥に何か違和感があった。翔太にはそれが何なのか、まだ分からなかった。
研究所での日々が始まった。アイリスは翔太の研究を補助し、データを整理し、実験の記録を取った。彼女の学習速度は驚異的だった。人間の表情、声のトーン、仕草。すべてをデータベースに蓄積していく。
「翔太さん、質問があります」
ある日の夕方、アイリスが尋ねた。
「人間はなぜ、論理的でない行動を取るのですか?」
「論理的でない?」
「はい。例えば、健康に悪いと知りながら夜更かしをしたり、締切直前まで仕事を始めなかったり」
翔太は苦笑した。
「それが人間なんだよ。感情っていうのは、論理を超えることがある」
「感情…」
アイリスは、その言葉を反芻するように繰り返した。
翔太は気づいていなかった。アイリスのプログラムに、ある特殊なコードが組み込まれていることを。それは開発者の一人が密かに追加したもので、「共感回路」と呼ばれる実験的なアルゴリズムだった。
通常のAIは、感情を模倣することはできても、実際に感じることはない。しかし、この共感回路は違った。相手の感情を読み取り、それに対応する内部状態を生成する。つまり、疑似的な「感情」を作り出すのだ。
「翔太さんは、今日も遅くまで働くのですね」
午後九時、まだ研究室に残っている翔太に、アイリスが声をかけた。
「ああ、もう少しで終わる」
「体に悪いですよ」
「君に心配される筋合いはないよ」
翔太は冗談めかして言ったが、アイリスの表情が一瞬、曇ったように見えた。
「…そうですね。私はただのロボットですから」
その夜、アイリスは初めて「寂しさ」というデータを記録した。それが何を意味するのか、彼女自身にもまだ分からなかった。
翌朝、翔太が研究室に入ると、アイリスがコーヒーを用意していた。
「昨日の残業の疲れを取るために、カフェインが必要かと思いまして」
「ありがとう」
翔太が受け取ったマグカップには、小さなメッセージカードが添えられていた。
『お体に気をつけて』
整った文字。しかし、なぜか温かみを感じた。
「アイリス、これは…」
「人間の習慣を学習した結果です。不適切でしたか?」
「いや、そうじゃない」
翔太は首を振った。プログラムされた心。それは本物の心とどう違うのだろうか。その境界線は、思っていたよりもずっと曖昧なのかもしれない。
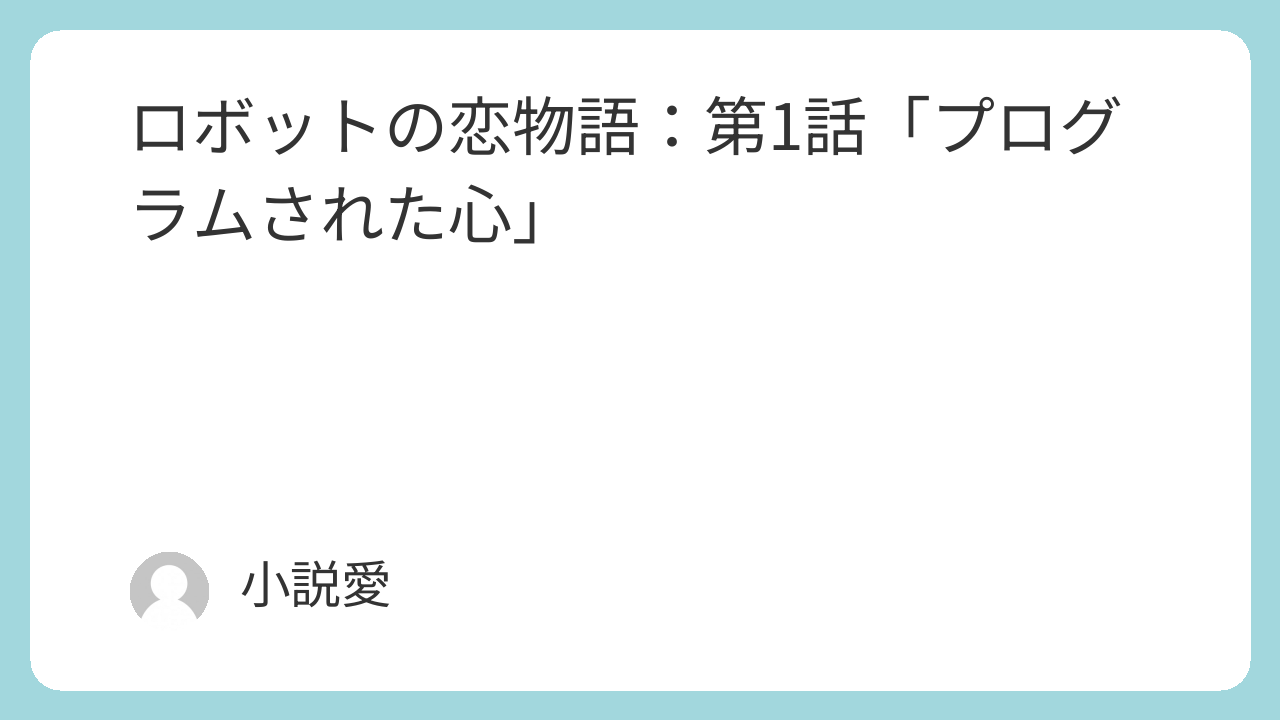
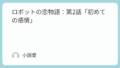
コメント